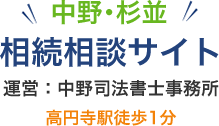認知症や精神障害、知的障害などが原因で判断能力が不十分になることがあります。そうすると預貯金や不動産などの財産管理、契約の締結なども難しくなってしまいます。
こんなとき、本人を保護・支援するのが成年後見制度です。
成年後見制度の一環では「成年後見登記」が行われるのですが、当記事では「成年後見登記とは何なのか」ということに重点を置いて解説していきます。成年後見登記を行うことでできるようになること、保護対象の本人や支援役となる後見人等がすべきこと、その他登記制度に関する基本的なルールも紹介します。
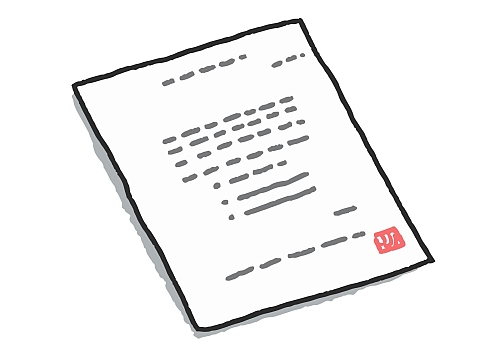
成年後見制度について
判断能力を欠いた、判断能力が不十分だという方は、介護のサービスの利用や施設への入所に関わる契約を結ぶのも困難になってしまいます。自らの財産を適切に管理し、守ることも難しくなってしまい、悪徳商法の被害に遭うリスクも高まってしまいます。
しかし、成年後見制度を利用すれば、判断能力の不十分な方を保護・支援するため、後見人が本人のサポートをしてくれます。
成年後見制度は大きく①法定後見制度と②任意後見制度の2種類に分けることができます。
法定後見制度には「後見」「保佐」「補助」の3つに分けることができ、本人の判断能力の程度に応じて後見、保佐、または補助が開始されます。
任意後見制度は、本人が事前に契約を交わすことで始められます。支援してほしい内容を契約に定めることができますし、後見人となる人物についても本人の希望を反映させることができます。
後見人等(保佐人や補助人なども含む)は、本来本人がすべき行為を代理で行ったり、本人のする行為に同意を与えたりすることでサポートします。後見人等の同意が必要な行為を本人がしてしまったとしても、後からその行為を取り消すことで不利益を防ぐ仕組みとなっています。
このように成年後見制度は保護対象となる本人にとってとても有益な仕組みなのですが、第三者に混乱を招くおそれがあります。契約相手が保護対象であることの判断が難しい場合、有効に成立したと思ったにもかかわらず、後から取り消されてしまうこともあるからです。そこで成年後見制度を利用していることが誰でも分かるように、「登記」を行うルールになっています。
成年後見登記とは
日本では、登記により公に情報を開示するという仕組みがあります。
不動産の権利関係について公示する「不動産登記制度」、法人の存在と一定の事項を公示する「商業・法人登記制度」などが代表例であり、これらに並んで成年後見制度の利用について公示する「成年後見登記制度」もあります。
成年後見人の権限や任意後見契約の内容等を登記官が登記することで、登記事項の証明が容易になります。つまり「成年後見制度を利用していること」あるいは「成年後見制度を利用していないこと」を示せるようになります。
成年後見登記によりできるようになること
成年後見登記によりできるようになることは、上述の通り「成年後見制度を利用しているかどうかの証明」です。
そう頻繁に必要性が生じるものではありませんが、場合によっては契約締結の場面で求められることがあります。雇用契約や売買契約、その他介護サービスに関する契約を締結するときなど、相手方が成年後見制度の利用有無について知りたい場面で求められます。
同制度を利用しているのであれば法務局にて手続を行い、登記事項証明書を提出。利用していないのであれば、登記されていないことの証明書を提出します。
成年後見登記制度における本人・後見人等の役割
登記に係る作業を直接行うのは登記官です。しかし登記官が登記を行うのは、各所から申請や請求を受けた場合です。
成年後見登記に関しては、本人や後見人等(成年後見人、保佐人、補助人、任意後見人など)ではなく、家庭裁判所や公証人による「登記の嘱託」をきっかけに登記官は登記を行います。
家庭裁判所が登記の嘱託を行うのは、法定後見開始の審判を行った場合と、任意後見監督人選任の審判を行った場合です。
これに対して公証人が登記の嘱託を行うのは、任意後見契約の公正証書を作成した場合です。つまり任意後見制度を利用するときは、本人と任意後見受任者が契約を締結したときと、実際にその契約に従った任意後見が開始されるときの2回、登記が行われます。
このように、成年後見制度利用の始まりに関しては、本人や後見人等が登記に関する手続を行う必要はありません。
しかしながら、変更登記の申請など次に挙げる手続については、家庭裁判所や公証人ではなく本人らが行うことになります。
- 変更登記の申請(登記されている人の住所変更等があったときに必要)
- 終了登記の申請(登記されている人の死亡等があったときに必要)
- 登記事項証明書の交付請求
- 登記されていないことの証明書の交付請求
なお、変更登記や終了登記についての申請は、各種監督人や親族などの利害関係人も行うことができます。
成年後見登記に関するルール

成年後見登記については、「後見登記等に関する法律」などに規定が置かれています。同法によると、成年後見登記についての事務は法務局や地方法務局、もしくはそれらの支局や出張所が行うものと定められています。これら登記に関する事務をつかさどる窓口は「登記所」と呼ばれたりもします。
証明書を発行してもらいたいときは、登記所に対して請求を行うと良いでしょう。
また、登記所での事務を遂行する者は「登記官」と呼ばれます。
法定後見制度における登記すべき事項
後見登記等に関する法律第4条第1項各号にて、法定後見制度を利用したときに登記すべき事項が規定されています。いくつかその内容を例示します。
- 後見等の種別(後見や保佐、補助の別)
- 後見等開始の審判が確定した年月日
- 被後見人等の氏名・生年月日・住所・本籍
- 後見人等の氏名(または名称)・住所
- 保佐人または補助人の同意が必要な行為
- 保佐人または補助人の代理権の範囲
- 登記番号 など
参照:e-Gov法令検索 後見登記等に関する法律第4条第1項
「保佐人や補助人の同意が必要な行為」など、その設定がなされたときに限り登記が必要になる事項もあります。
任意後見制度における登記すべき事項
任意後見制度についても、同法第5条各号で登記事項が規定されています。法定後見制度との違いに基づき、登記事項にも差異があります。
- 任意後見契約の公正証書を作成した公証人の氏名・所属
- 任意後見契約の公正証書の番号・作成年月日
- 本人(被後見人になる予定の方)の氏名・生年月日・住所・本籍
- 任意後見受任者または任意後見人の氏名(または名称)・住所
- 任意後見受任者または任意後見人の代理権の範囲
- 任意後見監督人の氏名(または名称)・住所・選任に関する審判確定の年月日
- 登記番号
参照:e-Gov法令検索 後見登記等に関する法律第5条第1項
法定後見制度と異なり後見の種別が分かれていないため、登記事項にも含まれていません。また、任意後見制度では事前に任意後見契約の公正証書を作成しなければならないため、その公正証書に関する登記事項が含まれています。
任意後見制度では①任意後見受任者、②任意後見人、③任意後見監督人の3者が必ず登場します。
①は、任意後見が開始されると②になる人物のことです。そして③は任意後見契約の内容が適切に実行されているかどうかをチェックする役割の人物です。任意後見制度では監督人の存在が必須です。
証明書の請求手続や手数料
成年後見登記についての証明書の請求は、全国の登記所で行うことができます。本人の住所地とは関係のない地域でも請求可能です。
※郵送での交付請求は東京法務局の後見登録課に限られる
手数料は、「登記事項証明書1通あたり550円」、「登記されていないことの証明書1通あたり300円」です。それぞれ収入印紙により納付します。
また、手続の際は本人確認ができる運転免許証やマイナンバーカードなどを持参しましょう。司法書士等の専門家に代理でお願いすることもあります。そのときは委任状や代理人の本人確認書類も必要になりますが、専門家の指示に従えば特に困ることはないでしょう。
- 時間外相談
- 当日相談
- 土日祝日相談
03-6272-4260
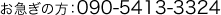
相談受付時間:平日・土日祝9:00~22:00営業時間:平日9:00~22:00
LINE・メール24時間受付/相談無料