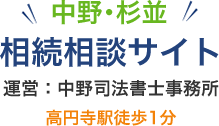亡くなった方の持っていた財産の多くは相続の対象となり、相続人が取得します。一方で相続ができない財産もありますし、相続とは別に契約や遺言書に従って取得する人物が定まるものもあります。「相続の対象になるもの」「相続の対象にならないもの」はどのように分かれるのか、ここで紹介していきます。

相続の基本的なルール
相続はある方が亡くなることで開始され、その方の持っていた財産が次の世代へと引き継がれていきます。
亡くなった方を「被相続人」、被相続人を引き継ぐ方を「相続人」と呼び、被相続人に配偶者がいるときは常に相続人になることができます。その他の方に関しては、事実上の身近な関係性の有無に関わらず、血縁関係に従い相続人かどうかが定まります。
もっとも優先されるのは被相続人の子どもで、子どもがいないときに限って親や兄弟姉妹などに相続の順番が回ってきます。そこで、以下に掲げる各種財産については相続ができるものであったとしても、各人が相続する権利を持っていないと取得することはできません。
また、法律上は相続人として認められる場合でも、被相続人が生前遺言書を作成しているときはその内容に従って財産が譲与されます。もしご自身が被相続人の妻や夫、子どもであったとしても、遺言書にて「すべての財産は友人Aに遺贈する。」などと記載されていると、やはり以下に掲げる財産であっても相続はできません。
これら相続の基本的なルールは覚えておいてください。
相続の対象になる財産
まずは「相続の対象になる財産」から紹介します。
現金や預貯金などの金融資産
相続の対象となる金融資産には、以下のようなものがあります。
- 普通預金
- 定期預金
- 当座預金
- 株式
- 投資信託
- 社債
- 国債
- 地方債 など
金融資産が残っているときは、各金融機関に連絡し、残高等の詳細を確認していきます。必要書類の内容や残高証明書発行の手続に関しては金融機関によって異なりますので、問い合わせるかWebサイトから確認をしておきましょう。
土地や建物
不動産も相続の対象となる財産であり、価額が大きいことから特に重要度の高い財産ともいえます。
土地や建物にも次のようにいろんな種類がありますが、すべて相続の対象です。
- 宅地
- 農地
- 山林
- 家屋
- アパート
- マンション
- 店舗
- 工場 など
なお、不動産を相続するときは遺産分割の方法に注意してください。
不動産は、金銭のように均等な分割ができないため、相続人間の利益バランスが崩れてしまうおそれがあります。そこで不動産をそのまま相続するスタイル(現物分割)にこだわらず、これを売却して金銭を分割する方法(換価分割)や、不動産の取得者が他の相続人に金銭を支払って分割する方法(代償分割)などもご検討ください。
自動車や貴金属などの動産

自動車や貴金属、その他亡くなった方の自宅にある家財道具なども相続の対象です。
これらは「動産」と呼ばれ、一つひとつの価値は小さいものが多いですが、骨董品や宝石類など単価の高いものが残っているケースもありますので注意してください。
また、動産も相続税の計算に含めるのが原則です。
一部の知的財産権
特許権や著作権などの「知的財産権」も、一部相続の対象になります。
例えば著作者人格権のような、特定の人物が持つことに意味のある権利については相続の対象外ですが、その他の財産的権利に関しては相続の対象です。
貸付金などの債権
物としての存在はありませんが、貸付金などの「債権」も相続することができます。
特に被相続人が事業者であった場合、取引先に対する売掛金など、注事業関連でさまざまな債権を残している可能性があります。そのため注意深く遺産の調査を行うことが大事です。
借金や住宅ローンなどのマイナスの財産

債権とは反対に、マイナスの価値を持つ「債務」についても相続の対象です。
例えば被相続人が借金をしていたり、住宅ローンが残っていたりすると、相続人がその債務を代わりに引き継ぐことになってしまいます。
※住宅ローンについては被相続人が亡くなることで残高がゼロになるケースもある。
そのため相続開始後の遺産調査においてはマイナスの財産についても漏れなく調査を行うよう注意してください。もしプラスの財産よりマイナスの財産の方が大きいとわかれば、「相続放棄」の手続も検討します。相続放棄をすれば相続人ではなくなりますので、プラスの財産を引き継げない代わりに借金などの肩代わりをする必要もなくなります。
相続の対象にならない財産
限定的ですが、いくつか相続の対象から外れる財産もあります。その代表的なものを紹介します。
被相続人に固有の一身専属権
被相続人本人でなければ意味をなさない、本人であることに意義がある「一身専属権」に関しては相続の対象外です。
そこで、貸付金などを請求する権利については相続することができますが、次のような権利については相続ができません。
- 代理権
- 雇用契約に基づく地位(従業員であることなど)
- 配偶者居住権や配偶者短期居住権(相続後の家屋に住み続ける権利)
- 生活保護の受給権
- 親権者の地位
祭祀財産
「祭祀財産」も相続の対象外です。これは祖先を祀るための財産であって、具体的には次のようなものが該当します。
- 系譜:代々の血縁関係をあらわした絵図や記録のこと。いわゆる「家系図」。
- 祭具:宗教によっても異なるが、例えば仏像・十字架・位牌などが挙げられる。
- 墳墓:遺体や遺骨を葬るためのもので、例えば墓碑・墓石・霊屋・埋棺などが挙げられる。
これら祭祀財産は相続するのではなく、被相続人の指定やこれまでの慣習に従い取得者(祭祀承継者)を定めます。もし慣習などがなく、遺言書による指定などもないときは、最終的に家庭裁判所が決めます。
「相続していいものなのかわからない」、または「どうやって遺産分割すればいいのだろうか」と悩むことがあれば司法書士に相談してください。プロが調べることですぐに問題を解決でき、その後取り組むべき手続についてもアドバイスをもらうことができます。
- 時間外相談
- 当日相談
- 土日祝日相談
03-6272-4260
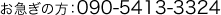
相談受付時間:平日・土日祝9:00~22:00営業時間:平日9:00~22:00
LINE・メール24時間受付/相談無料