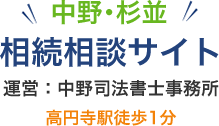資産管理・運用の手段として近年話題によく取り上げられる「信託」ですが、その仕組みは複雑で、誰もが利用する身近な制度といえるほど普及はしていません。しかし、適切に信託を活用すれば、他の制度だと実現が難しいことでも叶えられることもあります。
そこで当記事では、「信託って何だろう?」という疑問をお持ちの方に向けて、基本的な知識を整理しました。ぜひ参考にしていただければと思います。

信託とは「他人を信頼して委託すること」
信託とは、「自分の財産を、信頼できる他人に移転し、委託した方の設定する目的に従い管理・運用してもらう」制度のことです。
実はすでにさまざまな場面で信託は利用されています。家族など身内間で利用(家族信託という。)されるほか、公益や福祉、企業のビジネスとして利用されることもあります。
実際、公証役場を利用した信託だけでも数千件規模で毎年行われています。
個人間で契約書を交わすこともできるため正確な件数を把握することはできませんが、信託の契約書を公正証書として作成することも多く、公証役場の記録から一部把握が可能なのです。
信託の目的
信託の目的はさまざまですが、大きく「財産の管理」「財産の運用」「財産の承継」に分けることができます。
- 財産の管理
将来のために財産を守ること。高齢者や障害者の財産管理を行うために信託が利用されることがある。
- 財産の運用
財産を効果的に運用して、増やすこと。不動産や有価証券などの資産を本人から預かり、より効果的な利用をする。
- 財産の承継
財産管理を担う受託者を介し、他人に財産を譲ること。金銭的なサポートにあたり、ただ譲るのではなく受託者による適切な管理の下で引き継ぐなどの取り決めも交わせる。遺言書の代用としても使える。
このように、信託は契約の内容次第でさまざまな目的を果たすことができ、多様なニーズに応えることができる制度です。本人が望めば身近な人に対してだけでなく、社会貢献を目的とした信託も可能です。自然環境の整備、学術分野の研究など、目的に合った場所へ寄付をすることなども契約で設定できます。
信託の種類
信託は、上に挙げた目的であったり受託財産であったりと、さまざまな観点から種類分けができます。
よくされる分類は、「民事信託」と「商事信託」です。財産を引き受ける受託者が営業として信託を行うかどうかで分けられ、営業として行う場合を商事信託と呼びます。そしてそれ以外の信託を広く民事信託と呼びます。
また、信託による利益を誰が受けるのか、という観点から「自益信託」と「他益信託」に分けることも可能です。例えば、自分の財産を守るためにする信託や、自分の財産を増やすためにする信託は自益信託となることが多いです。これに対して、増やした財産を他人のために使ったり、財産を承継したりする信託などは他益信託と呼ぶことができます。要は、後述する「受益者」が、委託者と一致するかどうかで区別されます。
信託の仕組み・構造
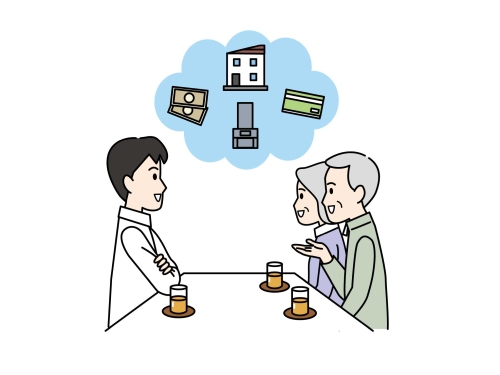
信託には、基本的に①委託者、②受託者、③受益者の3者が登場します。委託者が預けた財産を受託者が管理運用し、その利益を受益者が受ける、という構造になっています。
委託者 | 自分の財産を託す人のこと。 |
|---|---|
受託者 | 託された財産を管理運用する人のこと。 契約で定めた信託行為に従い、信託の目的を果たすために必要な行為を行う。 未成年者や成年被後見人、被保佐人は受託者となれない。 |
受益者 | 信託財産から生じる利益(信託受益権)を得る人のこと。 委託者と同一人物が受益者となることもある。 |
信託契約に基づき、受託者に属することとなった財産を「信託財産」と呼んでいます。
信託財産は処分できることが重要であり、金銭的価値に見積もることができる財産であれば広く信託することができます。動産や不動産、物件や債権など、さまざまな財産が信託可能です。
信託をするとどうなるのか
信託をしない場合、財産を所有する方が自ら管理運用し、財産を守っていかないといけません。認知症などにより判断能力が衰えてしまうと上手く取り扱うことができなくなりますし、詐欺被害に遭うリスクも高まります。そこで、信託をすることによりこの問題を解決することができます。
また、資産運用など財産を増やすための行為に関しては成年後見制度で対応するのが困難ですし、遺言書を使ったとしても承継できる範囲がかなり限定されます。信託であれば、資産運用や相続に対して自由度高く取り組むことが可能なのです。
それぞれ、信託でどのように対処できるのかを説明していきます。
委託者が認知症になっても適切な財産管理ができる
認知症が進行すると、判断能力が低下し、単独で有効に法律行為を行うのが難しくなってしまいます。本人が難しいと感じるかどうかとは別に、後から無効と評価されてしまうリスクが高まってしまうのです。本人だけで契約を交わすこともできなくなります。
認知症をきっかけに本人の財産が悪用される可能性もありますし、そのような事態を知った銀行が口座の凍結を行うケースもあります。
また、本人が所有する不動産も処分が困難となります。家族であっても自由に代理で売却するといった行為はできません。
こうして何もできない期間が長くなると、「財産を使えず生活に困ってしまう」「資産価値が下がってしまう」といった問題も出てきます。
しかし、事前に信託の契約を交わすことで認知症対策を取ることが可能です。元気なうちに受託者を選定し、財産を託しておけば、その後判断能力を欠いたとしても資産凍結などの問題を避けられます。
柔軟性の高い資産運用ができる
判断能力が不十分になった方を法的に保護する制度として「成年後見制度」もあります。法律行為などのサポートを行う後見人等が付き、本人の代理人として機能する、本人のする行為に同意を付すなどして支援を行います。
しかし、成年後見制度は本人が不利益を受けないようにすることが主な目的であり、財産管理を任せることはできても、財産を増やすための資産運用までは任せられません。
これに対して、信託であれば、株式投資や不動産投資といった積極的な財産の運用も委託することが可能です。
委託者についての相続対策になる
信託は相続対策としても有効です。よく知られているのは遺言書を使った対策です。どの財産を誰に譲るのか、遺言書にその内容を記載することで、法的な拘束力を発揮することができます。
ただ、遺言書の場合は二次相続以降の承継についてまで指定することはできません。「次の承継者」までしか定めることができず、「さらにその次の承継者は○○とする」といった指定は効果を発揮しません。
一方信託は、二次相続以降の、世代を超えた財産承継の指定が可能です。
このように信託にはさまざまな利点があります。その他の手段とも比較検討して、利用を考えてみると良いでしょう。検討にあたっては法律の専門家に相談することをおすすめします。
- 時間外相談
- 当日相談
- 土日祝日相談
03-6272-4260
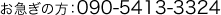
相談受付時間:平日・土日祝9:00~22:00営業時間:平日9:00~22:00
LINE・メール24時間受付/相談無料