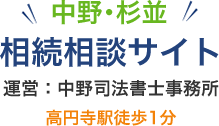信託は始めるまでの契約手続などが大変で、専門家がついていないと始めるだけでも一苦労です。
ただ、本番は信託がスタートしてからです。当事者は各々に認められている権利や義務に沿って、必要な行為を行うこととなります。
信託の当事者である受託者、委託者、受益者それぞれについて、信託開始後することを説明していきます。

受託者がする仕事内容
受託者は、委託者から財産を託された人物です。信託開始後一番重要な役割を担う人物であり、信託が上手くいくかどうかは受託者として選ばれた人物の手にかかっています。
まずは信託財産と個人の財産を分別管理
受託者は、委託者との間で交わした信託契約に基づいて仕事を遂行していくこととなるのですが、まずは「信託財産と個人の財産を分別管理すること」が必要です。
これは「そうした方が良い」ということではなく、「信託法で規定されている法律上の義務」です。
信託財産と受託者の個人的財産が混ざると適切な管理ができなくなってしまいますし、信託財産にかかる債権者としても対応に困ってしまいます。
そこで受託者は個人財産との区別をはっきりさせなければなりません。
その上で、受託者には「善管注意義務」が課せられています。要は、十分に注意して信託財産を管理しなければならないという意味です。
また、次の義務も受託者には課されています。
- 忠実義務
信託法および信託目的に従わないといけない。
- 帳簿の作成や報告等の義務
信託財産については記帳を行い、計算書類を適切に作成すること、そしてその保存や報告をしないといけない。
信託の目的達成のための様々な行為をする
適正な信託のため、受託者に対しては数多くの義務が課せられていますが、広範な権利も持っています。
信託財産に関して、「信託目的を達成するために必要な行為をする権限を持つ」と信託法でも定められています。
そこで信託がスタートすると、受託者は次のような行為を始めます。
- 信託財産を保管・運用するため、修繕費の支出や、賃貸物件における家賃の受け取りなどができる。
- 信託財産に属する財産を売却・譲渡する権限があり、株式の取引、土地の売却などもできる。
- その他、信託の目的の達成に必要ないろんな行為ができる。
信託が始まり費用の負担を受託者が負ったときは、その分を信託財産から支払う必要があります。
また、契約で定めたときは信託財産から受託者に対する報酬の支払いも発生します。
信託開始後に委託者ができること

自らの財産を託して信託を開始する人物が委託者です。
信託財産は、元は委託者個人の財産ですので、信託契約締結の主導権を握るのも委託者です。信託がスタートしてからも強い権限を持ちます。
信託財産に対する直接的な行為は受託者に任されますが、その受託者による権利の濫用を防ぐ役割を委託者は担います。
そこで信託開始後、委託者は次の権利を行使して信託を見守ることとなります。
- 信託の状況に関して報告を求める権利
受託者に対して「きちんと信託事務ができていますか」と確認するため、報告の請求ができる。
- 受託者の解任や選任をする権利
受益者との合意に基づき、受託者を解任することもできる。
- 契約に基づく指図権
信託契約に定めることで別途委託者に権利を与えることができる。例えば指図権を定めることで事業承継を円滑に進めやすくなる。
信託開始後に受益者ができること
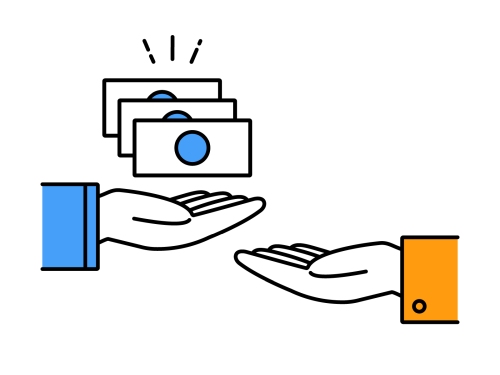
受益者は、信託による利益を受ける人物のことです。
※委託者と受益者は兼ねることができ、家族信託では委託者兼受益者となるケースも多い。
信託財産の所有権は形式上受託者に移転しますが、経済的な利益を受けるという実質の面においては、信託スタートに伴い受益者に財産が移るとも考えられます。実際、信託のスタートにより受益者には贈与税が課税されることがあります。
このような関係にあることから、受益者にも受託者の行為を監視する権限が与えられています。
例えば次のような権利を受益者は持ちます。
- 受託者の行為を取り消す権利
受託者が違反行為をはたらいたとき、その行為を取り消すことができる。
- 受託者の行為の差止めをする権利
違反行為を起こしそうな場面において、事前にこれを差し止めることもできる。
- 信託の状況に関して報告を求める権利
受託者に対して信託事務の状況を報告するよう求めることができる。
- 損失のてん補を請求する権利
受託者の懈怠により信託財産に損害が生じたとき、受託者に対して損失をてん補するよう求めることができる。
適切な信託とするための仕組み
信託開始後、基本的には受託者が契約内容に沿って仕事を始め、委託者や受益者がその状況をチェックしていくこととなります。
ただ、専門知識の乏しい委託者と受益者が受託者の行為を監視して評価するのは簡単なことではありません。
また、認知症であったり障害を持っていたりして本人による権限の行使が難しいケースもあります。
こうした問題を解決するため、信託では次に挙げるような仕組みが設けられています。
信託監督人・信託管理人による信託事務のチェック
受託者の仕事を監視する専門の人物として「信託監督人」を選任することができます。
信託目的を達成すること、円滑に信託事務を遂行させること、受益者の利益を保護することなど、信託全体が健全であることを目指します。
基本的には信託契約で選任について言及しておく必要があります。
しかし信託をスタートしてからでも、利害関係人が裁判所に申立てを行い、信託監督人を選任してもらうことは可能です。
同様に、信託事務の適正維持を図る「信託管理人」という人物も選任することができます。
こちらは受益者がいなくなってしまったなどの事情があり、一時的に信託事務の状況を管理する人物が必要となったときに置くものです。
受益者代理人による受益者の保護
受益者は複数人置くこともでき、そのときの信託監督人はすべての受益者のため、信託全体のために監督を行います。
これに対して「特定の受益者のため」に選任されるのが「受益者代理人」です。
信託全体を見渡す役割ではなく、ある受益者の代理人となり、当該受益者の代わりに権限を行使するのが役割となります。
ただし受益者代理人を選任するには信託契約でその定めを置いておかなければなりません。受益者が将来的に自らの権利を行使できなくなるおそれがある、契約当初から不安がある、といった場合には選任できる状態にしておくことも検討しましょう。
- 時間外相談
- 当日相談
- 土日祝日相談
03-6272-4260
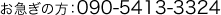
相談受付時間:平日・土日祝9:00~22:00営業時間:平日9:00~22:00
LINE・メール24時間受付/相談無料