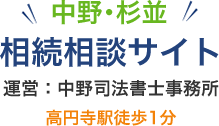ご自身の財産を他人に委託し、特定の目的に従って財産の運用をしてもらうことを信託と呼びます。さまざまなシーンで信託は利用されており、利用シーンによって信託の種類も異なります。
「家族信託」や「民事信託」、「投資信託」や「商事信託」などは聞いたことがあるのではないでしょうか。当記事ではこれら信託の種類を紹介、整理していきます。

民事信託と商事信託の違い
信託は、大きく種類分けすると「民事信託」と「商事信託」に分けることができます。
受託者が営業として信託を行う場合には商事信託、それ以外の信託が民事信託として区分されます。
信託全般には信託法が適用されるところ、商事信託には信託業法がさらに適用されるなど、ルールにも違いがあります。違いを下表で比較します。
| 商事信託 | 民事信託 |
|---|---|---|
受託者 | 受託者は金融機関など特定の事業者に限定される | 事業者に限らず受託者になれる |
目的と費用 | 受託者は営利目的で信託契約を交わすため費用も原則発生する | 目的は問われず報酬が発生するとは限らない |
信託財産 | 「金銭のみ」と指定されるなど事業者によって信託財産にできるものが限定されているケースが多い | 不動産や未上場株式など幅広く信託財産にできる |
根拠法 | 信託業法と信託法 ※信託業法の内容が優先される | 信託法 |
特徴 | ・プロに委託できる ・長期運用でも安心できる ・信託できる財産の幅が狭い ・コストが高い | ・財産の幅や運用の方法についての柔軟性が高い ・無報酬でも可能 ・能力不足で期待通りの資産運用ができない可能性がある |
民事信託と家族信託の違い
「家族信託」という用語を目にしたこともあると思います。家族信託は民事信託の1種で、当事者が家族や親族など、身近な方で構成される民事信託を特に家族信託と呼ぶことがあります。厳密な定義はなく、一般的な民事信託とルール自体に違いもありません。
家族信託の例
家族信託として信託の仕組みが活用される例に、「認知症対策」や「相続対策」が挙げられます。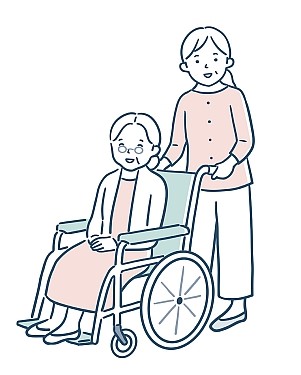
認知症になることで判断能力が衰えたりなくなってしまったりすると、それ以降自分自身で法律行為を行うことは困難になってしまいます。そうすると生きるために必要な財産の管理やサービスの契約などができなくなりますし、資産運用も難しくなってしまいます。
成年後見制度により法的支援を受けることもできますが、財産を増やすための積極的な資産運用は同制度の対象外です。これに対し家族信託は自由度が高く、あらかじめ委託者となる本人が受託者との間で運用方法を決めておけば、本人の望む通りに財産を任せられます。
また、死後の信託財産の取り扱いについて定めておけば相続対策として家族信託を利用することもできます。遺言書でも同様の効力を生じさせることはできますが、二次相続まで含めて対策を取るには信託の仕組みが効果的です。
「委託者が亡くなった後、信託による利益を得る受益者はAとする。Aが亡くなった後の受益者はBとする」などと定めて長期的に自らの意思を反映させることが可能です。
受益者の違いによる信託の種類
信託財産は、形式上は受託者の所有下に入ります。しかし、運用の結果生じる利益は受益者の手に渡ります。受託者には信託財産等から報酬が支払われますが、商事信託でない場合は報酬が発生しないこともあります。
そして受益者は、委託者と兼ねて設定することも可能です。この場合の信託は「自益信託」と呼ばれます。認知症対策で家族信託を始めるときなど、家族信託の多くはまず自益信託として設定されるケースが多いです。
一方、委託者と受益者が一致しない信託は「他益信託」と呼ばれます。信託で増やした財産を他人のために使うときや、財産の承継を目的に信託するときは、他益信託となるよう当事者が設定されます。
商品の違いによる信託の種類

商事信託の場合、各事業者が独自の信託商品を展開しています。
例えば不動産の信託、生命保険の信託、遺言の代用としての信託、投資信託など、ライフステージに合わせて多様なサービスが提供されています。名称や種類分けはサービスを提供する事業者により異なります。
個人向けではなく、法人向けに金銭債権や株式、担保権などの信託サービスを展開している例もあります。
- 時間外相談
- 当日相談
- 土日祝日相談
03-6272-4260
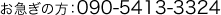
相談受付時間:平日・土日祝9:00~22:00営業時間:平日9:00~22:00
LINE・メール24時間受付/相談無料