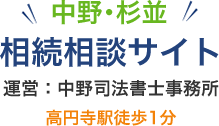信託の仕組みを活用することには次のメリットがあります。
- 適切な財産管理を維持しやすい
- 積極的な資産運用を任せられる
- 長期的な資産承継も指定できる
- 差し押さえ等の影響を受けない
これら各メリットについてここで解説し、また、家族・親族内で信託を始めることの利点についても紹介していきます。

適切な財産管理を維持しやすい
財産の信託を行うことで、それまで財産を持っていた委託者は自ら管理事務を行う必要がなくなり、他人に任せることができます。
委託者自身で適切に管理ができる間は大きなメリットがあるとはいえませんが、高齢の方など、認知症に対する不安を持つ方にとっては将来の不安材料を取り除くことにつながりますので利用価値は大きいです。
信託をした時点で所有権は受託者に移りますので、仮に委託者の判断能力がなくなってしまっても当初の契約に基づいて適切な財産管理を継続することができるのです。
また、元々管理等が複雑で扱いに困っている財産に関しても、信託で大きなメリットが得られます。例えば共有している不動産がある場合、賃貸に出したり大きな修繕を行ったりするにはその都度複数人で意見を合わさなければならず、管理上の手間が大きいです。
共有不動産の扱いをめぐって揉めるリスクも高いですが、信託しておけば管理事務も円滑化し、トラブルも起こりにくくなります。
積極的な資産運用を任せられる
認知症対策として「成年後見制度」も挙げられます。しかし同制度は「判断能力が衰えた本人が不利益を被る事態を避ける」ことを主な目的としています。
そこで投資用の株式を持っている被後見人がいたとして、後見人がいると、第三者に騙されて株式を贈与するような事態は避けやすくなります。しかし後見人が株式取引を積極的に行い、資産を増やしていくことは基本的に認められません。
所有している不動産を投資用に活用するといった行為に関しても同様です。後見人に求められているのは被後見人本人の保護であって、財産を増やすことが目的ではないため、投資の代行などは期待できません。
しかし信託では積極的な資産運用も可能です。
長期的な資産承継も指定できる
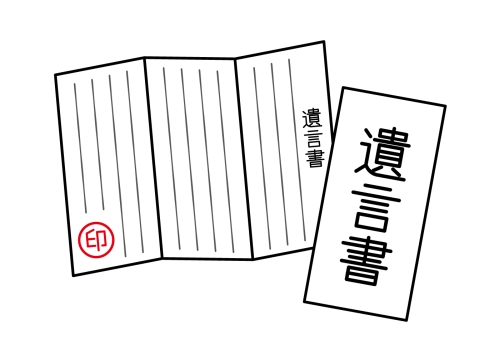
信託を活用して、長期的な資産承継も指定することができます。
委託者が亡くなった後、誰に財産を取得してもらうのか、この問題は遺言書を使っても解決することはできます。遺言書で承継先を指定しておけば、委託者に関する相続において特定の人物に特定の財産を受け取ってもらうことができます。
しかし遺言により実現できる資産承継は、遺言者自身について相続が開始される場合のみです。そこで資産の承継先として定めた方が亡くなったその後のことまで指定することはできないのです。
一方、信託の場合はこうした二次相続以降の対策も取ることが可能です。次の承継先、さらに次の承継先、そのさらに次・・・と、長期にわたる取得者が定められます。
また、そのときの管理方法・運用方法についても契約で定めることができますので、委託者が亡くなった後の配偶者や子どもの生活を守ることにもつながります。そこで障がいのある子どもの生活が不安だという場合などにも信託が活用されています。
差し押さえ等の影響を受けない
信託財産は委託者のものではなくなりますので、委託者がその後自己破産をすることになっても、差し押さえなどの対象にはなりません。信託財産を管理する受託者においても同じことがいえます。
信託財産の管理権限は受託者にあるとはいえ、経済的な利益を得ているのは受託者ではありません。受託者個人の財産とは独立した存在であり、受託者が破産をすることになってもやはり差し押さえのリスクにさらされることはないのです。
この独立性は信託財産の大きな特徴で、この性質があることによって遺産分割や遺留分などの対象からも外れることがあります。委託者の財産ではない以上、委託者が亡くなっても信託財産は相続財産とは分けて考えられますし、遺留分の主張によって当然に信託財産が回収されるわけでもありません。
※遺留分とは相続人の一部に法律上留保される遺産のこと。信託財産が遺産と評価されない以上、遺留分の対象財産からは除外されるが、「遺留分として財産が取られることを避けるために信託を始めた」という場合はその限りではない。
家族信託であることのメリットとは
信託サービスは銀行などの事業者が提供していますが、家族や親族内で契約を交わして信託を始めることもできます。この場合の信託は特に「家族信託」と呼ばれ、①じっくり話し合ってから始められる、②契約内容を柔軟に定められる、などのメリットがあります。
委託者の思いを汲んでもらいやすい
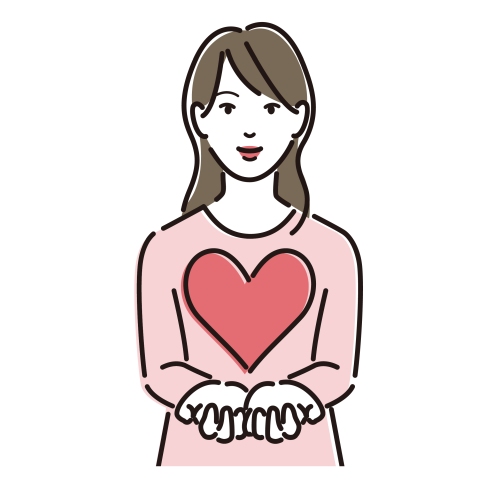
家族信託である場合、契約当事者の関係性が近いことから、委託者の思いを汲んだ上で信託を始めやすいというメリットがあります。
これまで抱えていた悩み、委託者の考え方、家族の暮らしぶりなどの背景をよく理解した人物が当事者になることで、より委託者の希望に沿った信託が期待できます。
柔軟性・自由度が高い
信託は、成年後見制度に比べると財産管理等に対する柔軟性が高いです。しかし事業者から提供されている信託サービスを利用する場合、ある程度決まった型で信託を始めることになります。
法律上は自由にカスタマイズすることが可能であっても、契約を根拠とする仕組みである以上、相手方の同意がなければ希望通りの信託事務は期待できないのです。ある程度の調整はしてもらえても、細かい指定・ルール作りなどに対応してもらえないことも十分に考えられます。
この点、家族信託であれば自由な設計がしやすいです。当然、受託者となる方の同意は必要ですが信託サービスを利用する場合に比べて柔軟に対応しやすくなります。
- 時間外相談
- 当日相談
- 土日祝日相談
03-6272-4260
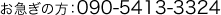
相談受付時間:平日・土日祝9:00~22:00営業時間:平日9:00~22:00
LINE・メール24時間受付/相談無料