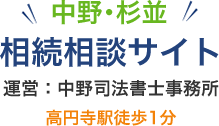予備の受益者を定めて信託を始めれば、特定の財産を子どもや孫たちへと代々引き継いでいくことができます。この信託は「受益者連続信託」と呼ばれ、遺言書などを使った相続対策ではできない財産の移転が実現できます。
どのように当事者を設定すれば受益者連続信託ができるのか、どのようにして財産が引き継がれていくのか、契約時に注意すべき点などもここにまとめました。

受益者連続信託とは
まず、信託には次の3者が登場することを押さえておきましょう。
- 財産を託す「委託者」
- 託された財産を管理する「受託者」
- 託された財産からの利益を受ける「受益者」
委託者と受益者は兼ねることもでき、この場合は財産の取り扱いについてのみ受託者に依頼することができますので、委託者自身の認知症対策としても活用されています。
一方で受益者を委託者と別の第三者に設定すれば、当該受益者は資産運用等の手間なく、利益のみを受けることができるようになります。
この受益者が亡くなることをきっかけに信託が終了することもあるのですが、途切れなく信託を続けたい場合は第2の受益者を定めることもできます。こうして次の受益者が予定されているときの信託を「受益者連続信託」と呼んでいます。
※次の受益者は「第2受益者」、さらに次の受益者を「第3受益者」と呼ぶ。
受益者連続信託では次のように信託が行われます。
- 委託者が信託契約を交わし、承継させたい財産を受託者に託す
- 第1受益者が亡くなると、受益権が第2受益者へと移転する
- 第2受益者が亡くなると、受益権が第3受益者へと移転する
資産を代々引き継いでいくことができる
受益者連続信託の契約を結んでおけば、これまで代々引き継がれてきた土地、子どもや孫たちに承継していってほしい資産など、特定の財産について望み通りに所有権を移していくことができます。
信託契約を結ばなくても相続の仕組みがありますので財産は自動的に次世代へと引き継がれていきます。しかしながら遺産分割協議によって事後的に定まりますので、誰に何が引き継がれていくのかが定かではありません。
一方の受益者連続信託であればあらかじめ定めた契約内容に沿って財産が移転していきますので、引き継いでほしい特定の人物に取得してもらうことができます。
子どもや孫が複数いるときでも、信託契約で「受益者は子Aとする。第2受益者は孫Bとする。第3受益者は・・・」などと定めておけば良いのです。
遺言書で承継できるのは一代先まで
信託の仕組みを使わなくても、遺言書を使えば遺産の取得者を指定することは可能です。
遺言の効力によって、指定された財産については遺産分割協議に優先して所有権を移転することができます。
ただし、遺言書で指定ができるのは一代先までです。
「土地Xは子Aに与える」とする遺言は有効ですが、さらに「子Aが亡くなった後は孫Bに与える」と遺言書に記載しても強制することはできません。子Aに関する相続の際、相続人たちが遺言書の内容に従わずに土地を遺産分割しても法的に問題はないのです。
事業承継も円滑にできる
受益者連続信託の仕組みは事業承継にも役立ちます。
ある会社の株式を持つ代表者が亡くなると、経営権を握る株式も相続の対象となり、後継者にしたかった子ども以外の手にも渡ってしまいます。相続人間の協議で後継者が取得するように遺産分割することもできますが、経営者不在の期間が生まれてしまうリスクがあります。
ここで株式を信託財産とし、後継者にしたい人物を受益者として複数指定して受益者連続信託を始めておけば、空白の期間も生まず円滑な事業承継が実現しやすくなります。
受益者連続信託をするときの注意点

信託の有効活用によって多くの課題を解決することができますが、適切に契約締結・運用をしていかなければかえってトラブルを招くことになってしまいます。特に受益者連続信託においては、受益者交代と信託期間の問題、受託者の設定について注意する必要があります。
30年経つと受益者の交代が制限される
交代できる受益者の数に決まりはありません。あまり一般的ではありませんが、第3受益者・第4受益者・第5受益者などと多くの受益者を設定することもできます。
ただし、未来永劫どこまでも連続させられるわけではありません。
信託法にて「信託開始後30年を経過してからできる受益者の交代は1回まで」と定められているからです。
受益者の死亡により、当該受益者の有する受益権が消滅し、他の者が新たな受益権を取得する旨の定め(受益者の死亡により順次他の者が受益権を取得する旨の定めを含む。)のある信託は、当該信託がされた時から三十年を経過した時以後に現に存する受益者が当該定めにより受益権を取得した場合であって当該受益者が死亡するまで又は当該受益権が消滅するまでの間、その効力を有する。
そこで、30年間が経った後で受益者が亡くなり第2受益者へと交代した場合、第2受益者の死亡によって信託は終了してしまいます。第3受益者が予定されていたとしても継続することはできません。
受託者と受益者が1年以上被ると信託が終わってしまう

“委託者”兼受益者と定めることはあっても、“受託者”兼受益者と定めることは通常ありません。財産の管理権限とそこからの利益を同一人物が受けることになり、単に委託者から財産の贈与を受ける場合と実質的な差異がないためです。
そこで信託法でも信託の終了事由の1つにも「受託者と受益者が一致する状態が1年以上続いたとき」が定められています。
(信託の終了事由)
受託者が受益権の全部を固有財産で有する状態が一年間継続したとき。
相続などが原因で受託者と受益者が一致してしまい、その状態が続いてしまうと信託は終わってしまいます。そのため受益者連続信託で多くの受益者を予定しているときでも、将来的に受託者と受益者が被ることのないように配慮すべきです。
受託者が不在にならないようにする
受益者連続信託では長期的に信託が続くと予想されますが、予備の受益者を定めるだけでなく「予備の受託者は必要ないか」についても検討することが大切です。
受託者が亡くなって新たな受託者が現れないまま1年が経過すると、信託は終了してしまいます。
(信託の終了事由)
受託者が欠けた場合であって、新受託者が就任しない状態が一年間継続したとき。
金融機関など法人を受託者として定めることもでき、この場合は個人とは異なり死亡のリスクがありません。長く続く信託にも対応しやすいですが、法人においても破産による消滅のリスクはありますので、受託者の定めについて留意が必要です。
- 時間外相談
- 当日相談
- 土日祝日相談
03-6272-4260
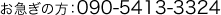
相談受付時間:平日・土日祝9:00~22:00営業時間:平日9:00~22:00
LINE・メール24時間受付/相談無料