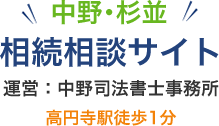家族信託は近年注目を集めている財産管理・運用の一手法です。これを相続対策や認知症対策として活用することもあります。
家族信託は委託者・受託者・受益者の3者から構成されるのが基本で、受託者が、委託者から任された財産管理等を行うことになります。そこで家族信託のキーマンとなる受託者に関して、さまざまな権限や義務が法定されています。
「受託者は具体的に何ができるのか」「法的にどのような権限が与えられているのか」についてここで解説します。また、適切にその権限を遂行する上では課された義務を順守することも大事です。この「受託者の義務」」についても簡単に紹介します。

受託者に認められる3つの基本的な権限
家族信託は、家族間で行う信託を指して呼びます。
そして業者ではない、一般の方がする信託については「信託法」に従うこととなります。
受託者は委託者から財産の管理を引き受けてその管理などを行います。委託者が受託者に預けた財産は信託財産と呼ばれ、その財産は委託者から受託者の所有下へと移ります。
受託者には信託財産を取り扱う権限が与えられるのですが、何でも自由に、受託者の裁量で取り扱えるようになるわけではありません。
基本的な権限が、次の信託法第26条に規定されています。
受託者は、信託財産に属する財産の管理又は処分及びその他の信託の目的の達成のために必要な行為をする権限を有する。ただし、信託行為によりその権限に制限を加えることを妨げない。
同条には次表の3つの権限が定められています。
信託財産に属する財産の管理 | 信託財産に属する多様な財産につき、保管・運用する権限 例:不動産の場合、家賃の受け取りや修繕費の支払い など |
信託財産に属する財産の処分 | 信託財産に属する財産を売却したり譲渡したりする権限 例:株式などの有価証券の売却、土地の売却 など |
その他の信託の目的の達成のために必要な行為 | 上の管理や処分に該当しないものの、信託契約に基づいて実行が必要になる様々な行為 |
「信託財産のためにした行為」であることが前提
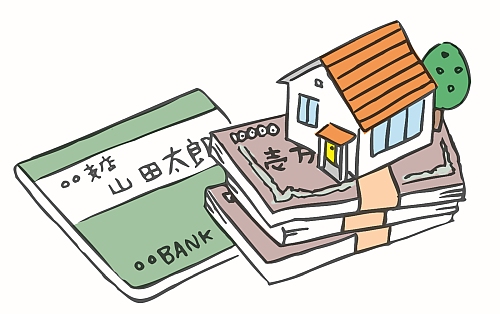
上に示した信託財産に関わる管理や処分については、受託者の権限として認められています。
ただし、その受託者のした行為による効果が信託財産に生じるためには、当該行為が「信託財産のためにした」といえる必要があります。
これは、行為から発生する利益や不利益といった経済的効果につき“信託財産に帰属させるものとして行った”という意味になります。
つまり、受託者の主観で捉えるのではなく、“行為の性質上客観的に信託財産へ効果が及ぶ行為”を指します。
逆に、「信託財産のためにした」ときでも受託者にその権限がないのなら、行為の相手方が「信託財産のためにした」ことを知らなかったときは、効果は信託財産に帰属しません。
これに対し、行為の相手方が「信託財産のためにした」ことを知っていたときは、効果は信託財産に帰属します。
信託事務処理の第三者への委託も可能
受託者は、自ら信託に係る事務を行うのが原則です。
しかし必ずしもあらゆる行為を1人でカバーする必要はありません。場面に応じて第三者への委託を行うこともあります。
これは「信託事務処理の委託」とも表現される行為で、信託法上も規定されている受託者の権限です。
受託者は、次に掲げる場合には、信託事務の処理を第三者に委託することができる。
一 信託行為に信託事務の処理を第三者に委託する旨又は委託することができる旨の定めがあるとき。
二 信託行為に信託事務の処理の第三者への委託に関する定めがない場合において、信託事務の処理を第三者に委託することが信託の目的に照らして相当であると認められるとき。
三 信託行為に信託事務の処理を第三者に委託してはならない旨の定めがある場合において、信託事務の処理を第三者に委託することにつき信託の目的に照らしてやむを得ない事由があると認められるとき。
例えば信託された土地上に建物を建築すること、訴訟への対応などの専門性の高い行為について、建設業者や弁護士に依頼する、といった場合です。
ただ、“建築や訴訟対応自体”を受託者の行うべき信託事務には含めず、“専門業者への依頼”が信託事務であると捉える考え方もあります。その考えに従うと、建設等の依頼をすることが同条における第三者への依頼にはあたらないともいえるでしょう。
他方、建設業者への依頼等が委託であると捉えたとしても、建築などの行為については専門の業者に委託するのが信託の目的に照らせば相当であると評価できます。
よって、どちらの考え方に従っても、専門性の高い行為につき専門家に依頼することは、信託法に背くことにはならないといえるでしょう。
信託事務処理の委託ができるケース
前項の信託法第28条各号は、信託事務処理の委託ができるケースをそれぞれ明記しています。
第1号はつまり「家族信託の契約書に委託をしても良いとの規定があるケース」を指しています。
信託財産の内容に応じて、事前に第三者への委託が想定されるなら、信託契約でその旨定めておくと良いでしょう。
第2号は、「信託契約に規定がないものの、信託事務処理の第三者への委託に合理的な理由があるケース」であるともいえます。
例えば、受託者自身が行うより高い技術やノウハウを持つ専門家を利用する方が適切な場合。あるいは業者に任せた方が効率的、コストパフォーマンスが高い場合などです。
第3号は、「信託契約に委託してはいけないとの定めがあるものの、委託せざるを得ない事情があるケース」のことです。
例えば、受託者が怪我や病気により対応ができない場面などが挙げられます。
信託事務処理の委託ができないケース
信託法第28条各号のいずれにも該当しない場合は、基本的に委託はできません。
そのため、委託をしても良いとの規定がなく、委託に合理的な理由もないのなら委託はできません。また、やむを得ない事由がなく、委託をしてはいけないとの定めがあるなら、そのときも委託はできません。
その一方、委託が認められる場面であっても委託の態様には注視する必要があります。
例えば「信託事務のすべてを委託すること」は名義信託にあたり無効になると考えられます。
実際、受託者が特定の業者の場合に適用される「信託業法」においては、信託業務のすべての委託は禁止する旨明記されています。
ただ、特定の第三者にすべてを丸投げするのではなく、各信託事務内容を鑑みて適切な委託先を選定し、結果的に幅広く信託事務を委託することになっても常に無効になるわけではありません。
各委託を個別に見て有効となるのであれば、信託全体としても有効になると考えられます。
信託財産から報酬や費用の償還を受けることができる

信託契約で定める信託行為に、報酬を受けることができる旨の規定が置かれている場合、受託者は報酬を受け取る権限を得ます。
そしてそのとき、基本的には信託行為に規定の計算方法に従うものとし、これがないときは計算の根拠を受益者に示して相当の額で請求することができます。
また、信託事務の遂行にあたって費用を支出したときは、信託財産からその費用+利息分の償還を受けることや、受益者に対して計算の根拠を示して前払いをしてもらうことも可能です。
信託財産からの償還では不足するという場合、受託者固有の財産を消耗していくことにもなりかねません。そのとき受益者への通知を行い、一定期間が経過しても費用の償還・前払いが受けられないときは、受託者は信託を終了させることもできます。
これらはすべて信託法に規定されていますが、信託行為の定めを別途置くことで、異なる取扱いをすることも可能です。
受託者には義務も課せられる
以上の受託者の権限とは反対に、受託者が守らないといけないルールもたくさんあります。
例えば次のような義務があります。
- 善管注意義務(十分注意して信託財産の管理をする義務)
- 忠実義務(信託法や信託目的に従う義務)
- 分別管理義務(受託者個人の財産と信託財産を分けて管理する義務)
- 帳簿の作成等の義務(信託財産に関する記帳を行い、適切に計算書類を作成・保存・報告する義務)
受託者はこれらの義務を果たしつつ、信託行為に従い、その権限を行使していかないといけません。
- 時間外相談
- 当日相談
- 土日祝日相談
03-6272-4260
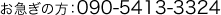
相談受付時間:平日・土日祝9:00~22:00営業時間:平日9:00~22:00
LINE・メール24時間受付/相談無料